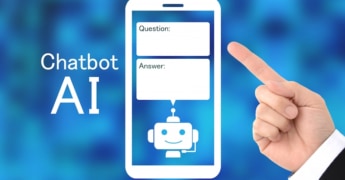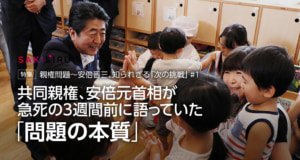「中国、民間企業の報道事業禁止案を公表」報道はミスリード?
有識者「10年以上前から同様の規定」- 中国政府が言論統制を強化するとのニュースが国内で報じられたが、実相は?
- 中国の識者は「10年以上前から同じ規定がある」と解説。大きな変化はなさそう
- 「報道機関はすべて官製メディア」中国社会の大原則を再確認したに過ぎない

北京市内の新聞販売スタンド(savoia /iStock)
10月9日、中国政府が言論統制を強化するとのニュースが各メディアで報じられた。
- 中国、民間企業の報道事業禁止案を公表 統制強める(日経新聞)
- 中国が言論統制を強化、民間の報道事業への参入禁止へ(読売新聞)
- 中国、民間企業の報道参入禁止案を公開 批判抑え込む狙いか(毎日新聞)
- 中国、民営企業のメディア経営禁止検討 報道規制強化か(朝日新聞)
いかにも独裁国家というニュースに、ツイッターでも大きな反響があった。
うわ、すごいのきた。歴史の変革・節目を見ている感ある。
reading… 民間に新聞、通信社、出版、テレビ、ネットニュースなどでの取材・編集を認めない。政治、経済、軍事、外交、重要な社会問題、文化、科学技術、衛生、教育、スポーツほか、世論を導く実況中継の禁止 https://t.co/DU6vFpRW1v
— 深津 貴之 / THE GUILD / note (@fladdict) October 9, 2021
中国が民間企業の報道事業を禁止するという。私が中国に行きだした2005年頃は、共産党幹部の中でも徐々に民主化していくだろうとの雰囲気があった、徐々に息苦しさが増し、この数年で一気に統制が進んだ。民主主義社会にあるブレーキ機能が中国にはないことを留意すべき。 https://t.co/d3og1PTi0S
— 細野豪志 (@hosono_54) October 9, 2021
どういうことなのか。現地のニュースを見て、確かめることにした。
現地報道を見てみると…
「政府が意見募集 非公有資本はニュースの取材編集、放送を行ってはならない」(央広網)との見出しで、確かに記事があった。中国政府が禁止事項を定めたリストが公開され、意見募集を行っているという。「金融機関でないものが金融取引をしてはいけない」などの項目に並んで、ニュース報道に関する禁止項目が確かにある。そこには、「非公有資本は、ニュースの取材編集、放送を行ってはならない」と記載され、ライブ配信をしてはならない、海外ニュースを報じてはならない、報道に関するイベント行ってはいけないなどの詳細があった。日本で報じられた内容は、この発表に基づいていると見られる。
「非公有資本」という聞き慣れない用語については、検索してもなかなか明解な答えが見出せなかったが、字義通りに解釈すれば、「公的でない資本」。さらに言えば、「政府の管理下にない組織」を意味すると理解して良さそうだ。「民間企業」と翻訳することはいささか乱暴にも感じるが、概ね間違ってはいないだろう。
中国のネット上でも、「これは失業警告だ」、「個人媒体は失業の準備をしなくては」などの声があり、不安視された。だが、一方で「従来通りの規定の延長に過ぎない」という解説記事も多数報じられた。
「非公有新本がニュース事業をできないとは? 専門家は『これまでの政策と同じ』と説明」(紅星新聞)との見出しの記事では、中国の記者協会(中華全国新聞工作者協会)で共産党組織の要職に就いていた経験のある中国伝媒大学の研究者、顧勇華氏を取材。記事によると、中国政府は遅くとも2008年時点で、「民間企業は新聞社、出版社、テレビ局等を設立・経営してはならない」との規定を作っているという。また、2018年、2019年にも今回とほぼ同様の禁止事項が発表されている。
「民間企業がニュース編集に関わってはいけないという規定は以前からあるもので、今回も重ねて明言しているに過ぎません」(顧勇華氏)
また、中国伝媒大学教授の王四新氏は、プラットフォーム企業やブログ等の個人媒体について、
「政治ニュースや国家運営に関わるニュースは制限を受けるでしょうが、科学技術や各業界の話題、知識の普及といった内容について、明確な決まりはない」
と説明。プラットフォーム企業は、ニュースの転載のみを行っているネット企業を指すと考えられる(日本で言うなら、ライブドアニュースやLINEニュース、独自取材を行う前の一昔前のヤフーニュースなど)。つまり、ネット企業がニュースを転載したり論評することについては、これまで通り、特に禁止されてないと見られる。
別の記事では、
「この規定は何年も前から存在したもので、メディア関係者は慌てる必要はない。通常の措置だ」(「騰訊新聞」掲載のコラム)
ともあった。現地の報道内容を見ると、大きく印象が異なる。今回の禁止案は、特に新しい措置ではないというのだ。日本の報道だけを見ていると、少々ミスリードに思える。

MoreISO /iStock
禁止案の背景:巨大IT企業を警戒?
日本でも多くの人に知られているように、中国では「ニュースは政府が管理する」のが大原則。人民日報や新華社通信、環球時報といった全国メディアのほか、北京日報、天津日報、新疆日報といった、各省の地方メディアが存在し、それらはすべて政府の管理下に置かれている。政府から独立した民間企業がニュース取材に関わることは、もともと想定されていないのである。
日経新聞はこう報じていた。
「中国では幅広い情報を扱う『微博(ウェイボ)』や経済問題を扱う『財新』などが人気を集めており、事業活動に影響があるかに注目が集まる」
だが、現地で報じられている内容を精査すると、その心配は当面はないようだ。特に「財新」については、北京日報や北京電視台といった伝統的オールドメディアと並ぶ「省級新聞単位」に位置付けられており、報道機関として一定の地位が確立されている。今回の規定によって、大きな影響が出るようには見られない。とはいえ、これは通達についてろくに説明をしない中国政府に問題がある。発表内容だけを読めば、さまざまな危惧を抱くのは当然だろう。
大手IT企業アリババの創始者、馬雲(ジャック・マー)氏は、かつてメディア業界にも強い興味を示していたという。巨大化するIT企業がニュース分野で影響力を持つことへの危惧は、政府のなかにあったのかもしれない。だが、今回の規定は「ニュースは政府の専売特許」、「報道機関はすべて官製メディア」という中国社会の大原則を再確認したものに過ぎないようだ。報道の自由がない国を“恐い国”と呼ぶなら、中国は建国から一貫して“恐い国”であり、それは今後も変わらないだろう。
中国について正しく認識するのは、とても難しい。恐ろしい国のようでいて、“幽霊の正体見たり枯れ尾花”ということも珍しくない。強権的な独裁国家であることは間違いないが、慎重に見極めたいものである。
関連記事
編集部おすすめ
ランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
 【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃
【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃 地震で伊達政宗像が傾く、歴史ファン嘆きの声「はやく直してあげて」
地震で伊達政宗像が傾く、歴史ファン嘆きの声「はやく直してあげて」 米中冷戦下の日本:小原凡司氏に聞く #3 対中戦略に必要な「理想と現実」の両輪
米中冷戦下の日本:小原凡司氏に聞く #3 対中戦略に必要な「理想と現実」の両輪 琉球新報また炎上!外部コラムニスト、ロシアのプロパガンダ “垂れ流し”批判招く
琉球新報また炎上!外部コラムニスト、ロシアのプロパガンダ “垂れ流し”批判招く 学校教育を救うには部活動全廃しかない
学校教育を救うには部活動全廃しかない 宮崎商 甲子園辞退で注目:朝日新聞の五輪コラムに特大ブーメラン!
宮崎商 甲子園辞退で注目:朝日新聞の五輪コラムに特大ブーメラン! 横浜市政「与党」共産党の市民アンケート、山中市長「期待した通り」わずか11%!
横浜市政「与党」共産党の市民アンケート、山中市長「期待した通り」わずか11%! 櫻井よしこ氏あぜん、共同親権「法務省案vs民間案」自民党内バトル勃発
櫻井よしこ氏あぜん、共同親権「法務省案vs民間案」自民党内バトル勃発 小室佳代さんへの刑事告発の動き、新聞・テレビが報じない不可解
小室佳代さんへの刑事告発の動き、新聞・テレビが報じない不可解 国民民主・玉木代表の「資産ゼロ」が話題、背景にとんでもないザル法の存在
国民民主・玉木代表の「資産ゼロ」が話題、背景にとんでもないザル法の存在
 SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します 【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃
【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃 トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか?
トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか? 東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大 ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も
ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も 韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った?
韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った? 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 「#金井米穀店を守れ」がトレンド入り。「騒動の現場」吉祥寺の店舗を訪ねた
「#金井米穀店を守れ」がトレンド入り。「騒動の現場」吉祥寺の店舗を訪ねた 「Tポイント」と「Vポイント」統合、加盟店離脱相次ぐ「Tポイント」は起死回生なるか
「Tポイント」と「Vポイント」統合、加盟店離脱相次ぐ「Tポイント」は起死回生なるか
 【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください
【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します 【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ
【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」
北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」 続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは
続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り”
ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り” 20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」
20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
特集アーカイブ
人気コメント記事ランキング
- 週間
- 月間