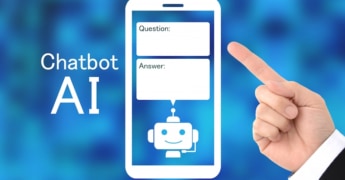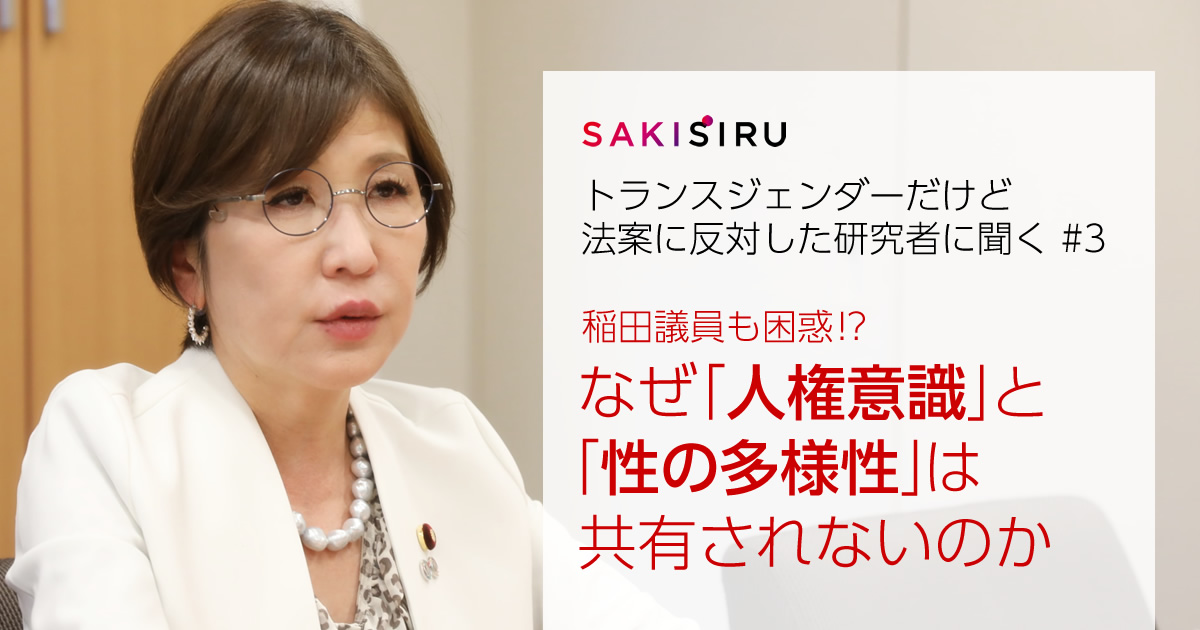朝日新聞記者の自殺報道に感じる、旧態としたメディア組織の構造
悲劇を繰り返さぬため、何が求められているか今週発売の文春砲の咆哮は、あまりにも物悲しく、救いのない響きしかなかった。朝日新聞大阪経済部の33歳の男性記者が10月6日に大阪市内のマンションで飛び降り自殺を図ったというのだ。この報道は文春以外に今のところ報道されておらず、テレビや新聞などの記者クラブメディアはできれば触れたくないだろう。

朝日新聞大阪本社が入る中之島フェスティバルタワー(ジュンP /PhotoAC)
しかし、ツイッターを見ると、朝日新聞関係者のアカウントがこの件には沈黙したり、朝日嫌いの右派アカが朝日を口撃したりといった「いつもの修羅の光景」があっただけではない。現役記者、あるいは近年記者を辞めた人たちの匿名アカウントによる嘆きや怒りが静かに広がっているのが窺える。元地方紙記者というアカウントは「ほぼ同世代だし、前職で自分もそれを考えたことがあったので全く他人事ではない。自分が選んだかもしれない未来かもしれなかった。なぜこうした悲しい事件が止められないのかな。業界としての病でさえあるんじゃないのか」と厳しく問いかけていた。
ツイッター投稿が波紋
波紋を広げたのは、当該の記者が死去直前にツイッターに意味深な内容を投稿していたからだ。文言が文春記事にあったため、同一人物と思われるアカウントはすぐにネット上で特定された。9月末までの投稿で特に異変を感じさせるものは見当たらないが、10月4日になり、
「重要な事実を探るために、権力者に近づくことはありますし必要です。ですが、なぜその記事をのせるのか、読者に堂々と説明できる論理がなにより大事だと思う」
と意味深な投稿を始め、
「紙面に意図的にのせて、権力者のご機嫌を取ってもたらされる情報って、本当に読者が求めているものなのかな。。トモダチだから書くってなったら、政権を「オトモダチ人事だ」って批判できなくなるのでは」
と述べ、紙面編成に何らかの不満があることを示唆。そして最後にこのようなツイートをしている。
「言うこと聞かない不良社員かもしれないけど、読者を一番に考えていると感じさせてくれたら、結構無理して働いてきたし指示にも従います。せめてうまく説得して、だましてほしいです」
「言うこと聞かない」「指示」と言う言葉から、上司との関係や組織と自分の折り合いに苦悩していることが十分うかがえる。そして、文春が朝日の関係者の証言を元に、自殺の要因になったと見ているのが、彼が担当していたパナソニックのリストラを巡る記事だ。早期退職に1000人超が応募し、その中には「活躍を期待していた人」(記事中の社長談話)までいたことは当時ツイッターでも話題になっていた記憶がある。もちろん、同社経営陣にとって思わぬことだったようだが、この記事が当時の上司である経済部長(11月1日付で東京本社に異動)に叱責されたと、文春は報道している。
そして、その記事の4日後、つまり彼が自殺する当日朝の紙面で、パナソニックのリストラについて「分社化による意思決定の迅速化」「改革」といった前向きな話が強調される記事が載っていたのだという。パナソニックは朝日に毎年5000万円の広告スポンサーでもあり、この当時の経済部長はビジネス部門も経験しており、営業サイド(広告?)との関係性が密な人物だったようだ。そして経済部の部下に商品紹介などの記事を書くように指示していたと言う話になっていて、自殺した記者とはソリが合わなかった経緯が掲載されている。

パナソニックの工場(winhorse /iStock)
悲劇が起きた構造:複眼視点の欠落
文春(と情報源)の見立てでは、こうしたプロセスからスポンサーの意向を気にする上司と、権力者との対峙を重視する記者との相剋が自殺の背景にあるという筋書きになっているようだが、仮にある程度、こうした背景や自殺との因果関係が事実だったとしよう。まず自殺やパワハラは本来あってはならない。そのことを議論の大前提とした、元記者としての私見だが、本件は価値観の違いすぎる上司と部下をうまく包摂できなかった組織構造が悲劇の要因に思えてならない。
経済部長はビジネス部門を経験し、自社の経営状態を気にかけるような人物だったようだから「経営者視点」が記者出身者にしては相当強いのだろう。だからパナソニックなど企業側に忖度したような指示を部下にしかできなくなる。
逆に亡くなった記者は、リストラ報道に際して経済部の記者にしては労働者側の視点に重きを置いていたようにも見える。
実際、彼は2日の記事を西村博之氏がツイッターで言及し、「経営者が、無能を切る事だけが『リストラ』だと勘違いしてるから、優秀な人もついでに居なくなっちゃうわけです」と論評した際に、西村氏に対し、「「能力に応じた適切な待遇」、とても難しい課題ですね。日本の企業ではチームワークが重視されることも多く、「成果」をうまくアピールできる人だけでなく、縁の下の力持ちや、サポート役もそれぞれ評価されるようになるといいですね。」と同調していたところからも、働く側の視点に重きを置いた企業取材をしている価値観が窺える。
企業のリストラは労働者にとっては退職や賃金カットなど人生設計に狂いが生じるのも事実だ。しかし経営者視点で見れば、津賀一宏氏が社長だった今年前半までの9年間、パナソニックはプラズマパネルからの撤退を始め、事業不信によるリストラに次ぐリストラだった。日立やソニーが復活する中で、次世代に向けた成長事業を作りきれず、津賀氏の後任となった楠見雄規氏は、まさにプラズマディスプレーの「店じまい」を取り仕切った人で、構造改革を厭わないと報じられてきた。

JHVEPhoto/iStock
組織と業界構造の老朽化
日本の新聞は事件や庶民を取材する社会部志向が底流になっているため、特に警察取材が多い若い頃は、消費者視点・労働者視点の「下流」からの眺めを向きやすくなるところがある。しかし、経済部記者は、経営者とも渡り合う「上流」からの風景を見て、事業を継続し、育て、あるいは不振ならどう打開していくか、その試行錯誤する様をもウォッチしていく感覚が欠かせない。
ただし、元日経新聞の牧野洋氏が著書『官報複合体』で指摘したように、日本の記者クラブ報道、特に経済分野は「上流」の視点にほとんど偏りがちで、消費者の意見が十分反映されにくい。逆に消費者側の意見は社会部の記者が取り扱うが、社会部の記者はビジネス素人のため、企業が何か消費者問題を起こした際、やたらに敵対的だったりする人がいて、取材で噛み合わないことが珍しくない。
今回の自殺の件はあえてインサイダー情報を持たずに、私なりに思うところを書いてきたが、経済取材であれ、政治取材であれ、「下流」と「上流」、複眼的に事象を見て分析し、本質に迫るのが、本来の理想形のように感じる。しかし結局は旧態とした取材の縦割り構造であったり、紙面作りであったりして、多様な価値観を反映させる鋭い記事制作を作りにくい組織構造、いや業界構造の「老朽化」があるのではないか。
悲劇を繰り返さないために何をすべきか。朝日新聞は、第三者委員会の力を借りてでも、安倍政権の不祥事に対して追及した努力と同じだけのエネルギーをぜひ真相解明に振り向け、そして外部への共有をやっていただきたい。次世代の新聞社再構築に活かすつもりがあるか本気度が問われている。
亡くなられた記者に心より哀悼の意を表する。
関連記事
編集部おすすめ
ランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
 ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? すしざんまい社長の海賊撲滅記事、プレジデントオンラインが削除でお詫び
すしざんまい社長の海賊撲滅記事、プレジデントオンラインが削除でお詫び 「#金井米穀店を守れ」がトレンド入り。「騒動の現場」吉祥寺の店舗を訪ねた
「#金井米穀店を守れ」がトレンド入り。「騒動の現場」吉祥寺の店舗を訪ねた 【Your Memorial News】2021年記事ランキング・トップ10
【Your Memorial News】2021年記事ランキング・トップ10 ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も
ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も プーチン氏の演説が中国でトレンド1位「私はロシアを無条件に支持する」
プーチン氏の演説が中国でトレンド1位「私はロシアを無条件に支持する」 共同親権問題:エマニュエル大使は、日本の連れ去り問題への対応を議会に約束していた
共同親権問題:エマニュエル大使は、日本の連れ去り問題への対応を議会に約束していた 4月30日、実は「プレミアムフライデー」だった
4月30日、実は「プレミアムフライデー」だった 給付金誤送金問題でネット注目、500万円の弁護士費用は「高過ぎ」か?
給付金誤送金問題でネット注目、500万円の弁護士費用は「高過ぎ」か? 部活推薦は「地獄への道」〜 工学部の入試に“アスリート枠”は必要か
部活推薦は「地獄への道」〜 工学部の入試に“アスリート枠”は必要か
 続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは
続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは 北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」
北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」 ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 【ニッポンジャーナル】衆院補選「大激戦」東京15区展望!
【ニッポンジャーナル】衆院補選「大激戦」東京15区展望! ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り”
ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り” 甲子園優勝の智弁和歌山・中谷監督、ネットで“携帯電話事件”が話題に
甲子園優勝の智弁和歌山・中谷監督、ネットで“携帯電話事件”が話題に 20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」
20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」 安倍元首相、布石を打ち始めていた共同親権
安倍元首相、布石を打ち始めていた共同親権 鳩山由紀夫氏が「疑獄の段ボール」63箱を引き取り、遺族の意向で立憲民主から入手
鳩山由紀夫氏が「疑獄の段ボール」63箱を引き取り、遺族の意向で立憲民主から入手 東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
 【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください
【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します 【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ
【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ 北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」
北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」 ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 防衛費増額なのに…弱体化した防衛産業をどう立て直していくか
防衛費増額なのに…弱体化した防衛産業をどう立て直していくか 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」
20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」 続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは
続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは 「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
特集アーカイブ
人気コメント記事ランキング
- 週間
- 月間