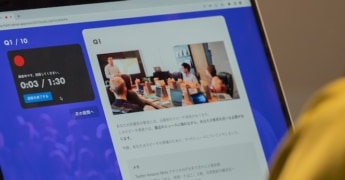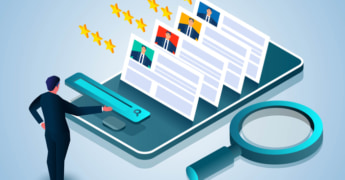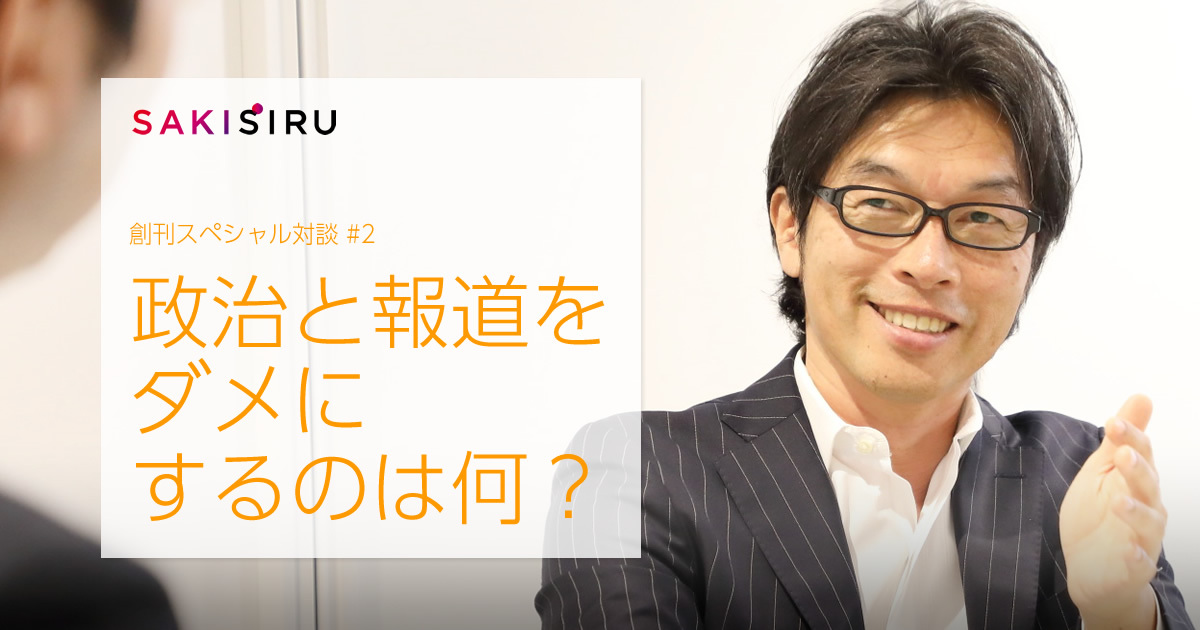「女性限定公募」は差別なのか? 〜 理系の女性研究者が少ない理由
東北大大学院の取り組みが賛否、論じたい“リケジョのリアル”- 東北大大学院工学研究科が女性限定で教授職を公募し、SNS上で賛否
- 「女性限定公募」の是非および、その背景にある問題点は?
- 女性研究者が少ない本当の要因は何か。当事者が指摘する「壁」は?
今年4月、東北大学大学院工学研究科が女性に限った教授職の公募を始めたことがSNS上で賛否を呼んだ。ただし教授職ではなかなか見られないものの、とりわけ理工系の学部において女性を優先して雇用するアファーマティブアクションは決して珍しくない。
国も大学も積極的に女性研究者の活躍を支援している。それでも、なかなか思うように増えていかない現状がある。「女性限定公募」の是非および、その背景にある問題点を考えてみたい。

metamorworks /iStock
女性の優遇措置は逆差別を産む?
東北大学は旧帝大時代の1913年(大正2年)、日本で初めて女性の入学を認めた歴史がある。多様性を尊重する精神は脈々と受け継がれ、4月には「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)推進宣言」を発出した。その看板策として教授職の女性限定公募を打ち出したが、SNS上では「それくらいしないと増やせない現実がある」と評価する意見の一方、「明らかな性差別」と批判する声も上がる。
マイノリティへの優遇措置であるアファーマティブアクションは1965年にアメリカで誕生し、いまや世界的な取り組みになっている。日本でも男女雇用機会均等法で性別を理由とする労働者への差別的な取り扱いを禁じた上で、男女間に格差が認められる場合に限り特例として認めている。
ただし法的に問題はなくても、同じポジションを狙う男性研究者が「能力ではなく性別だけで判断されるなんて」「逆差別ではないのか」とやりきれない思いを抱えてしまうのはやむを得ないだろう。アファーマティブアクションには、マジョリティ側が不満を持ってしまうといった弊害は確かにある。
それでも東北大が踏み切った背景には、研究者割合の顕著な男女格差がある。2020年時点で女性研究者の割合は28.6%。中でも理学分野で15.1%、工学分野で11.9%と、特に理工系において顕著に少ないことがわかる。たとえ男性に差別意識はなくとも、格差は女性が不利な状況を作り出す上、多様性の欠如や競争力の低下にもつながる。
格差是正に向け、文部科学省は女性研究者の登用・活躍推進に向けた補助金を支出。大学側も主に若手向けの任期付きのポジションで「女性限定」や「女性優遇」を前面に押し出した採用を実施したり、ライフイベントに応じたサポートを行ったりと、それぞれに腐心している。
女性は「理系に向いていない」?
女性の研究者が少ないのは、そもそも理系に進む女子学生が少ないことが大きく影響している。「感情的な女性よりも論理的な男性の方が理系に向いている」。多くの日本人が、ぼんやりとこのような認識を持っているのではないだろうか。
しかし、「女性は理系に向いていない」という思い込みは、昨今の研究データによって否定されている。たとえば、国際的な15歳時の学習到達度調査であるPISAの結果を見ると、数学では女子よりも男子の方が10ポイント高いが科学では同程度であり、OECD加盟国全体で見ると平均を大きく上回る。日本の女子学生はアメリカの男子学生よりはるかに優秀だ。
内閣府は、理系に進む女子が少ない背景として「学力不足ではなく、周囲の女子の進学動向、親の意向、ロールモデルの不在等の環境が影響している」と指摘 している(参照:内閣府「男女共同参画白書」)。つまり、「女子だから理系はできなくてもいい」という社会通念が理系分野に進む女性の数を減らし、結果として女性が少ない様子を見て「やはり女性は理系に向いていないんだ」との考えが強化される負のスパイラルが発生しているのだ。
研究者の「家庭との両立」は難しい
一方、男女共同参画学協会連絡会の調査によると、女性研究者が少ない要因として「教育環境」を挙げた女性研究者自身は約2割にとどまる。最も多くの回答が寄せられたのは「家庭と仕事の両立が困難」で6割超、次に「育児・介護期間後の復帰が困難」「職場環境」「男女の社会的分業」が4割超と続く。
環境要因を乗り越えた女性研究者にとっても、育児と仕事の両立はハードだ。女性研究者の多くが「子どもを持ちたい」と思いながら約3分の2に子どもがいない現状があり、その理由として「育児とキャリア形成の両立」を挙げる声が4割超と最も多いことからも困難さがうかがえる。

somethingway /iStock
成果を挙げた男性研究者の口からはしばしば、「24時間研究に打ち込んで…」「家庭のことは妻に任せっきりで…」といった言葉が飛び出す。研究の世界に終わりはない。自分の替わりもいない。女性研究者の配偶者には男性研究者が多いこともあり、このような環境下で育児を行うことはそもそも難しい。
なんとか子どもを授かっても、保育の壁に打ちのめされる。いわゆる出産適齢期と呼ばれる30代前半までの時期、研究者の多くは博士課程在籍中か3年程度の任期付きのポジションに就いている。育児休業を取得するには「1年以内に雇用関係が終了しないこと」が要件となる。任期付きのポジションに就いていた際に妊娠し、雇い止めにあった研究者もいる。
また、これらのポジションでは実際の稼働時間はどうであれ、保育園入園にあたってはフルタイムで働く女性より低い点数を付けられる事例が目立つ。運良く入園できたとしても、3年の任期では子どもの在園中に次のポストへの就職活動が始まり、保育園を新たに探さなくてはならない場合も多い。ある研究者は「やむなく認可外保育園に入れたが、収入の7割が保育代に消えた」と話す。
「女性限定」めくじらを立てる前に
そのような女性を支援するため、保育環境を整備している大学も増えている。特に国立大学では、2016年段階で半数以上が学内保育園を設置。ただし、一般の保育園より使いづらい園も多く、研究に集中できるどころか妨げになっているケースもある。東京大学では、自治体の保育園に落ちることが学内保育園の利用の条件となっており、一度学内保育園に入園しても、その後自治体の保育園に受かれば転園を強いられる。
また国公立大学では設置者が大学の場合、数年ごとに運営事業者の入札が求められることから、保育環境が安定しづらい背景がある。学内で3園を運営する大阪大学では、入札をめぐる不安定な雇用に端を発し、3月にある園では園長が退職。別の園でも園職員が9人退職し、穴埋めができていないまま運営が続いている。保護者や保育士らはこの事態に大きな不安を覚え、今年度に入り保育の安定化を求める動きを活発化させている。
研究者に能力主義を謳うことはたやすい。だが、現状は女性が能力を十分に発揮できる環境ではない。女性研究者自身に「『研究が好き』という気持ちだけじゃやっていけない現実がある」と言わしめている状況だ。アファーマティブアクションも環境を整える上で有効な施策の一つではある。
そこに目くじらを立てるより先に、思い込みの撤廃といったソフト面から保育施設の充実、2つ以上の機関に所属できるクロスアポイントメント制度の全国的な運用や子どもの保育園卒園を見据えた柔軟な雇用制度といったハード面まで、男女が一致団結してできることはまだたくさんあるはずだ。
関連記事
編集部おすすめ
ランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
 【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃
【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃 小学校に寄付をしたら確定申告を:寄附金控除のしくみ
小学校に寄付をしたら確定申告を:寄附金控除のしくみ 「女性限定公募」は差別なのか? 〜 理系の女性研究者が少ない理由
「女性限定公募」は差別なのか? 〜 理系の女性研究者が少ない理由 横浜市・山中市長の公約「3つのゼロ」達成ゼロで、新聞は追及モードになるか?
横浜市・山中市長の公約「3つのゼロ」達成ゼロで、新聞は追及モードになるか? フランスで公共放送受信料の撤廃へ、マクロン大統領が選挙時の公約果たす
フランスで公共放送受信料の撤廃へ、マクロン大統領が選挙時の公約果たす 親子を断絶する「DV支援措置」謎ルールが生む3つの“バグ”
親子を断絶する「DV支援措置」謎ルールが生む3つの“バグ” 20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」
20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 行政による動物「殺処分ゼロ」は本当か
行政による動物「殺処分ゼロ」は本当か ガソリン価格「200円超え」SNSで報告相次ぐ、トリガー条項の凍結解除いつに?
ガソリン価格「200円超え」SNSで報告相次ぐ、トリガー条項の凍結解除いつに?
 SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか?
トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか? 東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大 ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃
【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃 「ネットで真実」がアダに…「認知領域の戦い」どう乗り越えるか
「ネットで真実」がアダに…「認知領域の戦い」どう乗り越えるか ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も
ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も 韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った?
韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った? 「#金井米穀店を守れ」がトレンド入り。「騒動の現場」吉祥寺の店舗を訪ねた
「#金井米穀店を守れ」がトレンド入り。「騒動の現場」吉祥寺の店舗を訪ねた
 【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください
【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します 【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ
【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」
北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り”
ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り” 20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」
20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」 続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは
続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは 「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
特集アーカイブ
人気コメント記事ランキング
- 週間
- 月間