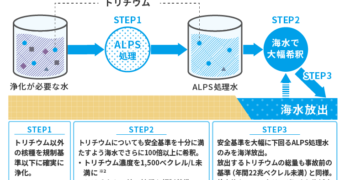「トンデモ医療」近藤誠理論に惹かれる人がいるのはなぜか?医師が自省したこと
「だまされないで」だけでは救えない難しさ- 「がん放置療法」近藤誠氏が急逝。なぜ人はトンデモ医療に騙されるのか?
- 患者と医師の認識差、「医学的に正しい」選択が患者本人に当てはまらないことも
- 医療側が鈍感になることもある「侵襲性」とは?トンデモ医療が入り込む「隙間」

放射線科医で、「がん放置療法」を提唱したとされる近藤誠氏が今月13日に急逝したことが、医療界および、医療発信を行うマスコミにおいて静かな話題となっている。
筆者は、近藤氏の訃報で、「近藤理論」や「トンデモ医療」が注目を浴びることは避けたかったため、ツイッターやウェブメディアでことさらに発信しないようにしようと思っていた。
ただ、近藤氏やそれに類する「トンデモ」に人々が惹かれる原因として、医療の側にも一部原因があるのではないだろうかと、医療に携わる者のはしくれとして、これまで何度となく思ってきた。そういった意味で、自省をこめて、近藤的なものがなぜ流行するのかについて書いてみたい。
なお、「近藤理論」は全てが「トンデモ」と断定できるわけではないことは、あらかじめ断っておきたい。
①コロナ流行でも示唆「患者と医療者のギャップ」
医師と患者の間には、多かれ少なかれ、コミュニケーションのギャップがあることがほとんどだ。病気に対する情報の量や経験が、医師と患者では圧倒的に違い、また、それゆえ、コニュニケーションに齟齬をきたし、患者さんが孤独感に陥る一因になることもある。患者さんが孤独になり、誰にも助けを求められない状態になると、「トンデモ医療」に頼ってしまうこともある。
医師をはじめとして医療従事者は、特に大きな施設では、日々、重症の患者の診療に明け暮れている。施設によっては、非常に幅広い症状や重症度の患者さんを診ることもある。とはいえ、「病状の重さや、実際に感じられるつらさ」に関して、患者の感じ方を正確に想像できるかというと、必ずしもそうではない。
例えば、新型コロナウイルスに実際に感染した医師たちは口々に、「軽症だったけれど、思ったよりつらかった」と口にしていた。わたしたち医療従事者は、「軽症」というと、その症状を客観的に診ているうちは、相対的に、それほどたいした病状ではないような印象を持ってしまうこともある。また、自身の家族ががんなどの病気にかかり、自身が診療していたときには思いもよらなかったことに気がついたという医師も多い。
目の前の患者さんの感じ方は千差万別で、ひとりひとりの感じ方や状況に寄り添うこと、とくに、癌治療をしている患者さんの肉体的、精神的つらさに、日々共感し、寄り添うのは簡単ではない。もちろん、多くの医療従事者は心身ともに疲れ果てている中で、仕事が山のように押し寄せている中で、できるだけ寄り添おうと努力している。
しかし、忙しさはときに想像力を鈍麻させる。多忙をきわめる大病院でも、患者を孤独にしないようなシステム、医療者の教育、マンパワーの拡充が望まれるのではないだろうか。
② その医学的選択が常に「最良」なのか?
現在、日本では、人生の最後を病院で過ごす人が多く、また、「がん」の多くは命にかかわる病態だ。だから、ついわたしたちは、医療を中心に患者さんの人生を考えてしまう。「命」という、有無を言わせない絶対的な価値の前には、他のことが、とても些細なことに思えてしまう場合もある。また、わたしたち医療従事者は、自分たちの体を、生理学的、解剖学的な主体・客体と考えることに慣れている。病気になったときにも、人にもよるが、エビデンスに基づいて、治る確率の高い治療を選ぶ可能性が高いかもしれない。
しかし、医療従事者以外の多くの人は、突然病気になって病院を受診するまでの間、医療とはほぼ無関係に生活を営みながら、人生を送る。だから、人の体について、誰もが解剖学的、生理学的なイメージを持っているというわけではなく、ある人にとっての身体のイメージは、物語のようなものに近いかもしれないし、あるいは触覚的なものかもしれないし、あるいは呪術的なものかもしれない。
わたしを含めた医療従事者はつい、患者さんにも生理的、解剖学的、確率論的に考え、選択して欲しいと願う。そうすれば、正しい選択が出来て、少なくとも統計的には、生存率はより長くなるはずだ。しかし気をつけなければならないのは、「医学的に正しい」選択が、価値観を含めたその人全体にとって、最良の選択となるとは限らないということだ。

また、様々な事情で、患者さんが「医学的に正しい」選択ができないこともある。わたしたち医療従事者ができることは、患者さんに十分な医療情報を提供し、患者さんが理解し、選ぶことができるようにすることだが、もし患者さんが、医学的に適切とはいえない選択をする場合、それを受け入れることが難しいと感じる医療者も多い。例えば、さまざまな理由で、患者さんは、十分になおるケースでも治療の拒否をすることがある。どのようにして患者さん本人を尊重し、医学的に適切な選択、不適切な選択を含めて、寄り添っていくかは、多くの課題が残されている。
特に気をつけなければならないことは、患者さんが「医学的に正解」であるような選択肢をとれない場合でも、「その判断や選択肢は劣っている」という見方をするのは適切ではなく、また、「知らないのが悪い」というわけでもない。どんな過程を経て、どんな選択をしたとしても、十分な説明をしつつ、その人を支援することが必要だろう。そうではない場合、患者さんは、医療従事者に冷たさを感じ、「トンデモ医療」の持つ「やさしさ」に惹かれてしまうことがある。
③ どんな医療も「侵襲性」がある
とくに軽い処置や治療では、医療者側は、その処置の侵襲性について鈍感になってしまうことがないわけではない。辞書によれば、医学における侵襲性とは「生体の内部環境の恒常性を乱す可能性がある刺激全般」を指し、投薬・注射・手術などの医療行為や、外傷・骨折・感染症などが例に挙げられる(参照:『デジタル大辞泉』)。
『軽症』という言葉に対して、医学と、一般の方のイメージのギャップがあることはすでに述べたが、侵襲性の少ない処置や、簡単な手術に関し持つ患者さんのイメージは、治療する側が想像するよりもずっと重いものであることもある。
検査にしてもそれは同じで、造影剤を入れて行う造影CTという検査があり、病院によっては1日100件以上も行われている「簡単な検査」だが、場合によっては造影剤のアレルギーで命に関わる症状がでることもあり、比較的被ばく線量も多い。造影剤がうまく血管に入らず皮下にもれたら、腕が腫れてしまうこともある。患者さんは、慣れない検査で緊張している上に、造影剤がはいっていくと、全身が熱くなるという体験をする。検査室に入るだけで恐怖を感じる人もいる。

場合によっては「簡単な検査」にも思える造影CTの検査ですら、デメリットは存在し、それを行うメリットがデメリットを上回るのか、厳密に判断する必要がある。手術や抗がん剤となると、なおさらだろう。
ときに、医療従事者は、デメリットを少なめに見積もってしまうこともあるが、そういったときは、医療の侵襲性について、基本に立ち返らなければならない。患者さんの、「侵襲性に対する恐怖感情」に寄り添えない場合、近藤氏の提唱した「がんの放置」のような、極端な結論を患者さんが導き出してしまうこともあるのではないだろうか。
④ 人が“近藤誠的なもの”に惹かれる理由
なぜ人は、「トンデモ医療」に惹かれ、ときに陰謀論を信じるのだろうか。医療記事では、それは、ときにはリテラシー不足によるものだとされ、SNSによるエコーチャンバーの影響だと書かれることもある。そういった解釈は部分的には正しいだろうが、病院の医療が、患者に完全に寄り添うことが、十分にできていないケースもある。
それは、必ずしも医療従事者の怠慢ではなく、病院のマンパワーや仕組みには課題が多い。治療の現場で、何らかの理由で、自己決定が十分に尊重されないように感じるケースもあるかもしれない。あるいは、その患者が受けるのにふさわしいケアが、病院よりも在宅の現場で提供されているものであったり、がんの場合は、積極的な抗がん剤治療よりも緩和ケアが適切な場合もあるだろう。トンデモ医療は、そういった「ケアの隙間」にうまく入り込み、ときに優しい言葉をかけ、そして、不安な状況に「寄り添う」。
それに対して、だまされないで、と、言うのはそれほど難しいことではないが、そういった注意喚起を、本当の意味で届けるのは難しい。だから、わたしたちは、「だまされないで」とただ言うのではなく、病院の仕組みを整えたり、地域社会でも、個人が孤立しない仕組みを整えていったり、より、人と人との個々の関係性に立脚した、全体的な取り組みが必要となるのではないだろうか。
■
【おしらせ】松村むつみさんの著書『自身を守り家族を守る医療リテラシー読本』(翔泳社)、好評発売中です。
関連記事
編集部おすすめ
ランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
 櫻井よしこ氏あぜん、共同親権「法務省案vs民間案」自民党内バトル勃発
櫻井よしこ氏あぜん、共同親権「法務省案vs民間案」自民党内バトル勃発 米中冷戦下の日本:小原凡司氏に聞く #3 対中戦略に必要な「理想と現実」の両輪
米中冷戦下の日本:小原凡司氏に聞く #3 対中戦略に必要な「理想と現実」の両輪 国民民主・玉木代表の「資産ゼロ」が話題、背景にとんでもないザル法の存在
国民民主・玉木代表の「資産ゼロ」が話題、背景にとんでもないザル法の存在 共同親権、安倍元首相が急死の3週間前に語っていた「問題の本質」
共同親権、安倍元首相が急死の3週間前に語っていた「問題の本質」 宮崎商 甲子園辞退で注目:朝日新聞の五輪コラムに特大ブーメラン!
宮崎商 甲子園辞退で注目:朝日新聞の五輪コラムに特大ブーメラン! 防衛省・自衛隊がドローンに本腰をあげた!日本は巻き返せるのか?予算から徹底分析
防衛省・自衛隊がドローンに本腰をあげた!日本は巻き返せるのか?予算から徹底分析 ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も
ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も 横浜市長選で初当選の山中竹春氏に「疑惑」横浜地検に刑事告発状提出
横浜市長選で初当選の山中竹春氏に「疑惑」横浜地検に刑事告発状提出 「女性限定公募」は差別なのか? 〜 理系の女性研究者が少ない理由
「女性限定公募」は差別なのか? 〜 理系の女性研究者が少ない理由 台湾有事シミュレーション「日米大損害も中国の台湾占領を阻止」から何を学ぶか
台湾有事シミュレーション「日米大損害も中国の台湾占領を阻止」から何を学ぶか
 SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します 【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃
【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃 櫻井よしこ氏あぜん、共同親権「法務省案vs民間案」自民党内バトル勃発
櫻井よしこ氏あぜん、共同親権「法務省案vs民間案」自民党内バトル勃発 東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も
ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか?
トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか? ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った?
韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った? 小室佳代さんへの刑事告発の動き、新聞・テレビが報じない不可解
小室佳代さんへの刑事告発の動き、新聞・テレビが報じない不可解
 【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください
【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します 【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ
【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」
北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」 20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」
20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは
続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り”
ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り” 「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
特集アーカイブ
人気コメント記事ランキング
- 週間
- 月間