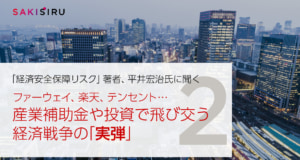2040年までに「EV、FCV100%」ホンダの「賭け」勝算あるか
「原点回帰」「脱サラリーマン体質」三部社長、問われる改革の成否- 「2040年までにEV、FCV100%」ホンダ三部社長の「賭け」
- 具体策殆どなしの高目標。「ホンダらしさ」原点回帰を追求
- 過剰設備と高コスト体質を克服し、稼ぐ力を取り戻せるか
ホンダの三部(みべ)敏宏社長は23日、就任以来初の記者会見をし、2040年までに四輪車の世界販売に占める電気自動車(EV)と燃料電池車(FCV)の比率を100%にする方針を明らかにした。30年に40%、35年に80%と段階的に高め、40年に目標を達成させる計画だ。
EVとFCVは、ハイブリッド車(HV)やプラグインハイブリッド車(PHV)と違って全く内燃機関(エンジン)を使わない。四輪にHV二輪と発電機などの汎用機用を加えると世界最大のエンジン会社であるホンダが大きな戦略の転換に舵を切った。

野心的な目標を掲げた三部社長(ホンダ公式サイトより)
具体策なしで高目標のワケ
20年にホンダは全世界で四輪車を約445万台売ったが、このうちEVとFCVはわずか1%にも満たない。ホンダはEVの商品化で完全に出遅れていた。これまでの計画では、30年までに全販売に占める電動車比率を約65%として、このうち15%をEVとFCVが占める見通しだった。
これだと全体の10%がEVとFCVで、残りはHVとPHVになる計画。それを大きく改め、まず30年時点で従来計画の4倍に引き上げる。このために24年には軽自動車のEVを投入するほか、今後5年以内に10車種のEVを世界最大の中国市場で販売していく予定だ。

ホンダ公式サイトより
ホンダの方針転換の背景には、すでに多くの報道がなされているように二酸化炭素の実質排出ゼロを目指す「カーボンニュートラル」の動きが世界規模で加速していることがある。菅義偉首相は日本も2050年にカーボンニュートラルを達成させる目標を掲げている。ホンダの現状の電動化戦略のままでは世界の流れから取り残されるとの危機感が、社長に就任する前から三部氏にはあった。
そこで就任後すぐに巻き返し策を打ち出してきたのだ。しかし、これは一種の「賭け」であると筆者は見ている。記者会見でも三部氏は「決め打ちしたシナリオは描かない。色々なことを言うと焦点がぼけるので、EV、FCVと言ったが、それは今手の内にある技術だからであって、これから新しい技術が出てくるかもしれない」と語った。
これは、具体策についてはほとんど何も決まってないということだ。敢えてトップが高い目標を明確に示すことで現場から様々な挑戦的なシナリオが出てくることを期待しているのだ。ここが大きなポイントである。
「異質で自由」な原点回帰狙う
最近のホンダには魅力的な商品がほとんどないうえ、世間が驚くような画期的な技術もほとんど出てこない。「ホンダらしさ」が問われていた。ホンダは、ベンチャー精神旺盛な創業者の本田宗一郎氏が裸一貫で会社を作り上げ、通産省に逆らってまでも四輪事業に進出して成功したイメージを今でも引きずっていることから、世間は常に斬新的なメイド・イン・ホンダの製品を求めてきた。しかし、率直に言ってその期待に応えられていない。
三部氏は「ホンダらしさ」とは製品のことを指すものではないと考えている。今年2月19日の社長交代を発表した記者会見で「ホンダらしさとは、社会課題や強い相手に向き合う姿勢のことだ」と三部氏は言い切った。過去を振り返っても、F1への挑戦、排ガスを劇的に削減させる米カリフォルニア規制への対応など、難題に取り組めば取り組むほどそのプロセスから新商品や新技術がでてきた。
三部氏自身が社内で「環境問題のエキスパート」と呼ばれる。若い頃、排ガス浄化システムのプロジェクトに入り、氏が中心となって開発した「極超低排出技術」は、カリフォルニア規制が強化される2年前に完成したと言われている。
ホンダ社内には、新社長は人と同じことをするのが嫌いなタイプではないかと見る向きがある。広島大学大学院で内燃機関を学んでいた頃の三部氏は、日産サニーを乗り回し、「皆が地元のマツダに行くから俺は金太郎飴みたいになりたくないので、ホンダに行ってF1をやりたい」と語っていたという。

ホンダが昨年発売したEV「ホンダe」(同社提供)
ホンダが元気な頃、研究開発部門ではよく「並行異質自由主義」とか「一件一人主義」と言われた。全社一丸の開発体制は採用せず、技術者一人ひとりが独自のテーマを持つという意味だった。特定の技術に決め打ちしないことで組織の「引き出し」を増やし、連帯責任にしないことで一人ひとりの責任感を持たせるためだった。
社内会議では、一件一人の開発テーマに対して否定的な意見を言う場合には、必ず代案を出さなければならない暗黙のルールがあったとされる。これは、リスクを取らない官僚的な上司が、部下の新しいアイデアを潰すことを避ける狙いがあった。
開発部門ではこうした働き方を徹底させることで、異端児たちがボトムアップで開発を進めていく風土ができた。これが「ホンダは自由な会社」と言われた所以でもある。
具体的な手段はほとんど決まっていないのに、三部氏が敢えて高い目標を打ち出したのには、この原点回帰を狙い、開発陣一人ひとりに「高い山」を登らせようとしているのだ。そうすることで、斬新な技術やアイデアが必ず生まれてくると信じているのだろう。
「脱サラリーマン」化の2大阻害要因
そのために引き続き潤沢な予算を投入する。三部氏は23日の会見で、「今後6年間で5兆円の研究開発費を投じる」と語った。過去6年間の累計比で約2割増となる。
ホンダの開発部門は子会社化されている。本田技術研究所のことで、三部氏は社長就任前のポジションは同研究所社長兼本社専務。すでに布石は打っており、研究所の体制を19、20年と続けて大規模に改編した。
量産に近い平凡なことしかやっていな技術者を、製造・販売を担う本社の四輪事業本部に大量異動させ、研究所は「失敗するような研究」しかしない組織と位置付け、誰もリスクを取らない「オールサラリーマン化」の風土を改めようとしている。先が見えていないような研究をしないと、驚くようなものは出てこないとの考えからだった。
こうして三部氏は原点回帰で「ホンダ復活」を目論むが、現実は厳しいものがある。ホンダの世界販売はトヨタの半分にも満たないが、研究開発費は年間に8000億円程度あり、トヨタ(1兆1000億円)の7割を超える水準にある。一方で20年4〜12月期の四輪事業の営業利益率は0.8%で、7.7%あるトヨタとは大きく差が開いている。
その主要因は過剰設備と開発投資効率の悪さによる高コスト体質にある。総資産からどれだけ収益を生み出しているかを示す総資産利益率(ROA)がそれを如実に物語っている。リーマンショック前の08年3月期には7.6%だったのが20年3月期は3.1%にまで落ちた。

shaunl/iStock
「稼ぐ力」を早く回復できるか?
前々社長の伊東孝紳氏が12年、世界販売目標を当時の40%増となる600万台に設定し、拡大戦略を取ったことが裏目に出た。「安く早く新車を開発しろ」との大号令の下、世界で生産能力を増強させたが、身の丈を超える規模拡大に品質管理が追いつかず、13、14両年にフィットが5回連続の大規模リコールを起こしてしまった
伊東氏は品質問題に関して引責辞任に近い形で15年に社長を退き、後任には八郷隆弘氏が就任した。氏は在任中の6年間、前社長が進めた拡大戦略の後始末に追われ、英国工場や狭山工場などの閉鎖を決めた。さらに莫大なコストがかかるF1からの撤退も発表した。
過剰設備の対策には目途が付いた模様だが、短期的には四輪事業の収益性が厳しい中、コロナ禍や半導体不足によって追い討ちがかかり、足元の業績がぐらついている。昨年発売した初の量産EV「ホンダe」も売れば売るほど赤字になるほど原価が高い。また、収益源の米国では「アコード」がこれまでのように売れず、北米事業の立て直しも急がなければならない。
稼ぐ力を早急に回復させないと、開発陣が夢を追うためのキャッシュフローが生み出せない。IT業界からの新規参入も強まっており、自動車産業は変化のスピードが速い。元々「弱肉強食」の産業だけに、もたもたしているとホンダは業界再編の渦に飲み込まれかねない。
関連記事
編集部おすすめ
ランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
 「ネットで真実」がアダに…「認知領域の戦い」どう乗り越えるか
「ネットで真実」がアダに…「認知領域の戦い」どう乗り越えるか 韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った?
韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った? 野田元首相が岸田首相に「幽霊見ていないですよね?」、国会で首相公邸が事故物件扱い
野田元首相が岸田首相に「幽霊見ていないですよね?」、国会で首相公邸が事故物件扱い 世田谷と芦屋…東西2大ハイソな街、20代首長は誕生するか?
世田谷と芦屋…東西2大ハイソな街、20代首長は誕生するか? 音楽エンタメでも、世界市場で”日韓の差”:何が明暗を分けたか?
音楽エンタメでも、世界市場で”日韓の差”:何が明暗を分けたか? いじめ防止法の問題点、弁護士サイドはどう改善すべきかと訴えているのか?
いじめ防止法の問題点、弁護士サイドはどう改善すべきかと訴えているのか? 「保健室の先生がソープランドで副業し懲戒免職」は処分として重すぎ?
「保健室の先生がソープランドで副業し懲戒免職」は処分として重すぎ? 半数近くが詐欺 !? 「火災保険」異常な値上げの裏で暗躍する悪徳業者
半数近くが詐欺 !? 「火災保険」異常な値上げの裏で暗躍する悪徳業者 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 日立が全社員「ジョブ型」雇用シフトが話題も、日経新聞が書かない「限界」
日立が全社員「ジョブ型」雇用シフトが話題も、日経新聞が書かない「限界」
 SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」
北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」 トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか?
トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか? 東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大 大谷に朗報!MLBが今季から両リーグでDH制へ、日本のセ・リーグでも導入なるか⁉
大谷に朗報!MLBが今季から両リーグでDH制へ、日本のセ・リーグでも導入なるか⁉ 報道されない“真実” !?「テレビを消す」が有効な節電法で再注目
報道されない“真実” !?「テレビを消す」が有効な節電法で再注目 韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った?
韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った? 「ネットで真実」がアダに…「認知領域の戦い」どう乗り越えるか
「ネットで真実」がアダに…「認知領域の戦い」どう乗り越えるか
 【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください
【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します 北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」
北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」 【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ
【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは
続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り”
ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り” 「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
特集アーカイブ
人気コメント記事ランキング
- 週間
- 月間