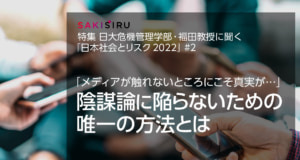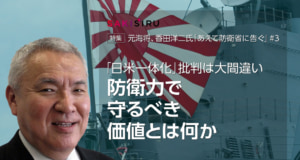【他メディア出演情報】1月15日
格差、飲酒運転、路上寝…「酒税減免」が蝕む沖縄の経済と社会
沖縄の自立を阻む酒税軽減措置をめぐる攻防 #2- 前回の流れから沖縄特例の酒税軽減措置の効果を検証。酒造所は一定保護
- 泡盛は本格焼より出荷減少幅が大。優遇税制を前提とした保守的な経営が背景
- 軽減措置で、安価に酒を入手でき飲酒運転や路上寝にも。措置廃止を主張
目下、政府と沖縄県とのあいだで、沖縄特例の酒税軽減措置の延長をめぐってちょっとした攻防がつづいている。沖縄県や酒造業界は延長を望んでいるが、果たしてそれでいいのか。「酒」をめぐる沖縄の闇に斬り込む。

Koenig /Photo AC
この記事は会員限定です。ぜひご登録いただき、続きをお読みください。サブスクなら読み放題です。
関連記事
ソフトバンク、KDDI社長とXで“共闘”も
「世界のATM」と紛争リスクの狭間
上半期決算発表、通期初の1兆円見通し
自動運転と日本社会【本記】
政策面・政局面待ち受ける困難
連載『日本経済をターンアラウンドする!経済再生の処方箋』#16
連載『日本経済をターンアラウンドする!経済再生の処方箋』#15
日本進出1年、リーマン破綻処理も経験
「民主主義のインフラに」ベリーベスト法律事務所
編集部おすすめ
ランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
 「ネットで真実」がアダに…「認知領域の戦い」どう乗り越えるか
「ネットで真実」がアダに…「認知領域の戦い」どう乗り越えるか 投資家に見放された岸田政権、「支持率たった3%」が話題
投資家に見放された岸田政権、「支持率たった3%」が話題 アイリスオーヤマが約50種類の製造を国内工場に移管、他社でも相次ぐ製造拠点の国内回帰
アイリスオーヤマが約50種類の製造を国内工場に移管、他社でも相次ぐ製造拠点の国内回帰 トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか?
トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか? 【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃
【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃 「空飛ぶクルマ」を支える「週一官僚」という働き方
「空飛ぶクルマ」を支える「週一官僚」という働き方 野田元首相が岸田首相に「幽霊見ていないですよね?」、国会で首相公邸が事故物件扱い
野田元首相が岸田首相に「幽霊見ていないですよね?」、国会で首相公邸が事故物件扱い 世田谷と芦屋…東西2大ハイソな街、20代首長は誕生するか?
世田谷と芦屋…東西2大ハイソな街、20代首長は誕生するか? 音楽エンタメでも、世界市場で”日韓の差”:何が明暗を分けたか?
音楽エンタメでも、世界市場で”日韓の差”:何が明暗を分けたか? いじめ防止法の問題点、弁護士サイドはどう改善すべきかと訴えているのか?
いじめ防止法の問題点、弁護士サイドはどう改善すべきかと訴えているのか?
 SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」
北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」 トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか?
トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか? 韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った?
韓国の反発で、佐渡金山の世界遺産推薦を見送りへ。期待していた地元民はどう思った? 「ネットで真実」がアダに…「認知領域の戦い」どう乗り越えるか
「ネットで真実」がアダに…「認知領域の戦い」どう乗り越えるか ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も
ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も 部活推薦は「地獄への道」〜 工学部の入試に“アスリート枠”は必要か
部活推薦は「地獄への道」〜 工学部の入試に“アスリート枠”は必要か
 【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください
【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します 【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ
【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ 北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」
北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」 ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大 続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは
続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り”
ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り” 「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
特集アーカイブ
人気コメント記事ランキング
- 週間
- 月間