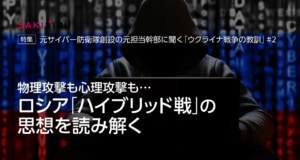「中国の台頭は終了」……だからこそ起こり得る「米中衝突」の危機に備えよ
米国の若手研究者らの刺激的な論文が話題に- 「中国の台頭はすでに終わった」。米の若手研究者らの刺激的な論文が発表
- 「力を失い追い詰められ、今よりもさらに攻撃的」論文の分析の妥当性は?
- 「現在の中国は89年から90年頃の日本と似たような状態」と筆者
「中国の台頭はいつまで続くのだろうか?」
これは東アジアの同じ地域で生きる日本にも大いに関係してくるため、我々が常に問い続けなければならない大きなテーマだ。2021年10月1日、この問いに対して、「中国の台頭はすでに終わった」とする刺激的な論文が発表された。

「北京は自暴自棄に」米外交誌論文の衝撃
掲載されたのは、外交専門誌として世界的に読まれている「フォーリン・アフェアーズ」誌のサイトである。
筆者はハル・ブランズとマイケル・ベックレー。それぞれ「大戦略」や「大国関係」を研究テーマとしている若手の研究者であり、ともに米国国防総省に役人として仕えた経験も持つ学者だ。
論文は大きく分けて5部構成になっている。ポイントは以下の通りだ。
- 中国の台頭は奇跡的な幸運のおかげ
- その幸運も尽きて「台頭」は終了した
- 最大の理由は成長の鈍化であり、経済的に厳しくなったこと
- 「反中包囲網」に戦略的に包囲されつつあること
- 危機を感じた北京は自暴自棄になりそうだ
彼らの議論が正しければ、中国の台頭はすでに終わっており、これから力を失う過程で立場的に追い詰められ、そのために今よりもさらに攻撃的になる――というのだ。
著者のブランズとベックレーは、議論を行う上で豊富なデータや事例を示しており、この論文そのものは実に説得力を持っている。
だが果たして、彼らの予測は本当に実現するのだろうか?
警戒されていた「30年前の日本」
国際政治において未来に起こることを予測するのはほぼ不可能に近いことだが、それでも過去の例を参考にすれば、ある程度のシナリオはイメージできる。
そしてその参考(アナロジー)として「30年前の日本」を使うことができる。

もちろん当時の日本と現在の中国は全く異なる。政治体制も異なるし、国の規模も違う。文化も成長スピードも違うのであり、一方はアメリカの従属国であり、もう一方は核保有国としてアメリカと対峙する気を持っている。そのため「そもそも比較対象として持ち出すことさえナンセンスだ」という人もいるだろう。
だが一方で日中は同じく東アジアの国としてアメリカという覇権国に対峙し、しかも経済的な結びつきが強かったこと、そして何よりもアメリカが「国力が抜かれるかもしれない」と警戒していた国という共通点はある。
「現在の中国」が、今後アメリカとどのような関係になっていく可能性が高いのか。本稿ではまず上記のブランズたちの論文の結論である「中国の台頭は終わった」が正しいものと一旦仮定しつつ、あえて「30年前の日本」を参考例として考えてみたい。
米中関係は悪化、世界は混乱へ
結論から言えば、米中関係はいまよりさらに悪化し、東アジアを中心に、世界はかなり混乱した状況に陥る可能性が高い。その最大の理由は、アメリカの反中姿勢のピークは、実際の中国の国力のピークよりも遅れて発生する見込みが高いからだ。
これは「30年前の日本」の例を考えてみればよくわかる。
日本とアメリカは同盟関係にあったにもかかわらず、すでに1980年代から日米間では貿易摩擦の問題を解決するために様々な協議が進んでおり、1988年には東芝がココムという共産圏への輸出禁止措置に違反して工作機械を東側に販売したとして、アメリカの連邦議事堂前で東芝のラジカセを叩き割るパフォーマンスも行われている。
この頃のアメリカからの苛烈な要求のために「ジャパン・バッシング」(日本叩き)という言葉も生まれたほどだ。
翌1989年の12月には、すでに米ソ首脳による冷戦終結宣言を受けて、日経平均株価が最高値をつけた直後から暴落をはじめた。この暴落を始める直前の日本を、戦後の台頭における国力の「ピーク」として考えることは可能であろう。
もちろんそのまま当てはまるわけではない。だが、ブランズとベックレーの分析が正しければ、現在の中国は89年から90年頃の日本と似たような状態にある、といえる。

「敵視の浸透」は遅れてやってくる
問題はその後だ。当時の日本はバブル崩壊によって不況に陥ったが、アメリカからは相変わらず日本を警戒するような言説が伝わってきていた。つまりアメリカの相手が「ピーク」を迎えても、その「敵視の浸透」には若干のタイムラグが出てくるということだ。
それが顕著に出るのは政治言論だが、エンターテイメントの分野でもアメリカが日本を「敵」のように扱った書籍や映画が出てきた。以下に代表的なものを挙げておく。
- 91年:映画『ザ・カミング・ウォー・ウィズ・ジャパン』→貿易戦争が第二次日米戦争につながるシナリオ
- 92年:小説『ライジングサン』→日本企業の陰謀を描く。映画は93年に公開
- 93年:映画『ロボコップ3』→日本企業が悪役。
- 94年:トム・クランシーの小説『日米開戦』→日航機のパイロットがワシントンへ飛行機で自爆テロして戦争勃発
この当時を生きていた人間としては、すでに経済力ではアメリカに追いつけないことが判明していたにもかかわらず、文化面で日本がまるで「敵」かのような扱いを受けていたのは、なんとも意外というか、やや衝撃的だった記憶がある。
ようするに日本の台頭のピークの時点でアメリカの日本敵視は十分激しかったのだが、その敵視を日本側が実感しはじめたのは、実際は90年代に入ってからであった。
中国は「チャイナ・バッシング」に耐えられるか
アメリカはその後も日本側に配慮のない行動を続けており、それが民主党政権のクリントン大統領が1998年6月に日本の頭越しで9日間も中国に滞在したことで頂点を迎えた。これが「ジャパン・パッシング」(日本通過)と皮肉な名前で呼ばれたことを覚えている方もいるだろう。
このようなことは、現在の中国に対しても起こる可能性がある。実際に中国の脅威そのものはピークを迎えていても、その認識やアメリカの敵視が本格化するには、若干のタイムラグが出てくるからだ。
しかも日本の場合は互いに同じ西側陣営に属していた同盟国同士で起こっていた話だ。政治体制も世界観も違い、しかも軍事的に太平洋の覇権をめぐって対峙している米中両国が、仮に中国の台頭のピークは今だとしても、このままおとなしく棲み分けができるとは思えない。
結論として、もしブランズたちの結論が正しければ、日本の事例から見えてくるのは、これから米中がいよいよ外交的に不安定な事態を迎えるという、やや悲観的な展望だ。そして日本は本格的に外交・安全保障面で悩まされることになる。
関連記事
編集部おすすめ
ランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
 参院選半年前で市井紗耶香氏がモー辞退、八幡和郎氏「泥船から逃げ出す人多し」
参院選半年前で市井紗耶香氏がモー辞退、八幡和郎氏「泥船から逃げ出す人多し」 ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り”
ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り” 「1ドル=129円」円安で留学に行けない!もはや“日本脱出”はムリなのか…
「1ドル=129円」円安で留学に行けない!もはや“日本脱出”はムリなのか… 「ユリコのパフォーマンス」1都3県の「まん延防止等重点措置」要請に疑問の声
「ユリコのパフォーマンス」1都3県の「まん延防止等重点措置」要請に疑問の声 7年前に逮捕で辞任した初の女性役員が復帰、トヨタが示したメッセージとは
7年前に逮捕で辞任した初の女性役員が復帰、トヨタが示したメッセージとは SAKISIRU「共同親権」訴訟結審、判決は3月8日
SAKISIRU「共同親権」訴訟結審、判決は3月8日 「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴
「共同親権」報道訴訟、SAKISIRU・西牟田氏が一審勝訴 石井紘基議員暗殺事件、“愛弟子”泉房穂・明石市長「国家を挙げてのもみ消し工作だった」
石井紘基議員暗殺事件、“愛弟子”泉房穂・明石市長「国家を挙げてのもみ消し工作だった」 「iPhone14」世界で2番目に安いのに…高すぎて買えない日本人が続出か…
「iPhone14」世界で2番目に安いのに…高すぎて買えない日本人が続出か… 行政による動物「殺処分ゼロ」は本当か
行政による動物「殺処分ゼロ」は本当か
 SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 櫻井よしこ氏あぜん、共同親権「法務省案vs民間案」自民党内バトル勃発
櫻井よしこ氏あぜん、共同親権「法務省案vs民間案」自民党内バトル勃発 トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか?
トヨタ「エース社員」退社続出は、“改革者”の豊田社長についていけないからなのか? ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り”
ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り” 参院選半年前で市井紗耶香氏がモー辞退、八幡和郎氏「泥船から逃げ出す人多し」
参院選半年前で市井紗耶香氏がモー辞退、八幡和郎氏「泥船から逃げ出す人多し」 【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃
【特報】滋賀県の市議会で自民党籍の議員「刺青」騒動、本人を直撃 東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大
東京23区の格差がネットで話題、1位の港区と23位の区の差は半世紀で倍に拡大 ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も
ゴーカート死亡事故で問われる大人の責任、ネットでは主催したトヨタ系4社追及の声も
 【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください
【ご支援のお願い】スラップ控訴に負けたくないです。助けてください SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します
SAKISIRU 4月末で本サイト閉鎖。note にアーカイブ移行します 【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ
【闘争宣言】SAKISIRUを提訴。Colaboとも一部重複する弁護団はコイツらだ ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」
北村晴男弁護士「共同親権、裁判所が利権失うのが怖い」 ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り”
ハンストから1年、東京家裁で男性敗訴。判決は、フランスの逮捕状にも“開き直り” 20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」
20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」 安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」
安芸高田市長にヤッシーが喝!田中康夫氏「やり方が下手っぴ。頭でっかちな偏差値坊や」 櫻井よしこ氏あぜん、共同親権「法務省案vs民間案」自民党内バトル勃発
櫻井よしこ氏あぜん、共同親権「法務省案vs民間案」自民党内バトル勃発 続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは
続・ジャニーズ私の「敗戦処理策」、真に罪に向き合う「基金」スキームとは
特集アーカイブ
人気コメント記事ランキング
- 週間
- 月間